【腰痛リスク】脚付きマットレスをおすすめしない2つの理由
更新日:
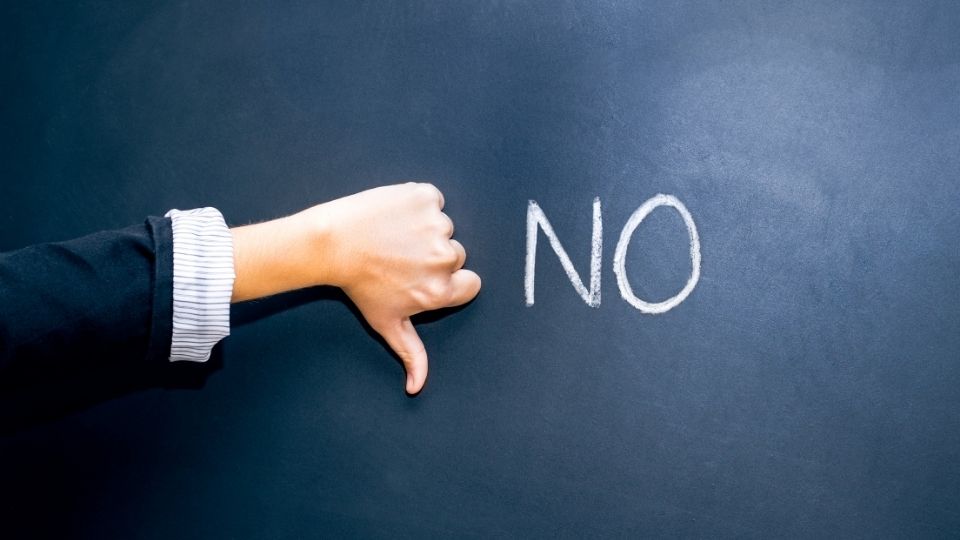
「あいつは脚付きマットレスに恨みでもあるのか?」
と言われることがある加賀照虎です、こんにちは。
脚付きマットレスは本当におすすめ出来ません。
恨みがあるわけではないのですが、どうしても寝心地がイマイチになってしまう理由があるから否定せざるを得ないのです。
そのため、
「脚付きマットレスを買おうかな」
と考えている方には、是非知っておいてもらいたいです。
ということで本日は「脚付きマットレスをおすすめしない2つの理由」についてお伝えしていきます。
| ※自分に合ったマットレスを選ぶ手順(型→素材→個別商品)と値段、体質、好み別におすすめできるマットレスについてこちらのページ「マットレスのおすすめ17選|専門家が教える自分に合うものを絞り込む手順」で徹底解説しています。脚付きマットレスベッドだけでなく多様な素材から網羅的にマットレス選びを進めたい方は是非ご参考にどうぞ。 |
1. 脚付きマットレスが向かない人の特徴とは?
脚付きマットレスは、省スペースで設置できたり引っ越しがしやすかったりと便利な面があります。しかし、構造上の弱点から人によっては合わないケースも少なくありません。ここでは、特に注意したい「脚付きマットレスが向かない人」の特徴を解説します。
1-1. 腰痛持ちの人
腰痛がある方には脚付きマットレスは不向きです。理由は、内部のコイル上に敷かれる「詰め物」が薄い構造が多いため、体圧分散が不十分になりやすいからです。
クッション性が弱いため、腰や背中の一部に圧力が集中し、寝返りのたびに負担がかかります。特に慢性的な腰痛持ちや、柔らかさと硬さのバランスを必要とする人には合わず、症状を悪化させる可能性があります。
1-2. 体重が重めの人
体重がある人の場合、マットレスの薄いクッション部分がすぐにへたり、底付き感を感じやすくなります。
結果的にコイルの硬さがダイレクトに体へ伝わり、快適な睡眠姿勢を保ちにくくなるのです。また耐久性の面でも、体重が重いほどコイルの劣化スピードが早まるため、長期的に使うには不安が残ります。
1-3. 寝返りの多い人
寝返りを頻繁にする人にとっては、マットレスの横揺れや分割部分の段差がストレスになります。特にセパレート式の脚付きマットレスでは、中央の硬いフレーム部分に腰や背中が当たり、痛みの原因になるケースもあります。
寝返りがスムーズにできないと、熟睡感が得られにくくなるため注意が必要です。
1-4. 耐久性を重視する人
脚付きマットレスは、一般的なスプリングマットレスに比べると寿命が短めです。ローテーションや裏返しができず、同じ部分に負荷がかかりやすいため、へたりやコイルの劣化が進みやすい構造になっています。
長く使える寝具を探している方や、コストパフォーマンスを重視する方には向きません。
1-5. デザインや収納性にこだわる人
シンプルさが魅力の反面、脚付きマットレスはデザインや機能性の幅が限られています。ヘッドボードがないため、枕元に小物を置けず、別途サイドテーブルが必要になることも。
また、脚付きマットレスは「マットレスとフレーム一体型」のため、マットレスだけを交換することができず、劣化すると丸ごと買い替えになってしまいます。長期的に見れば不便さを感じる人も多いでしょう。
2. 脚付きマットレスをおすすめしない2つの理由
重大なポイントから順に解説していきます。
2-1. コイルの上に詰め物が少なく、腰を痛める恐れがあるから
まずは、おすすめできない最大の理由から。
前提知識として、脚付きマットレスはほぼ全てコイルスプリング製です(つもりポケットコイルもしくはボンネルコイル)。
| 種類 | イメージ | 体圧分散 | 反発弾性 | 横揺れ | 通気性 | お手入れ | ||
|
ノ ン コ イ ル |
高 反 発 ・ 高 弾 性 |
高反発ウレタン フォーム |
|
◯ | ◎ | ◯ | △ | ◯ |
| ラテックス |
|
◯ | ◎ | ◯ | △ | ◯ | ||
| TPEポリマー |
|
◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ||
|
中 間 |
一般ウレタン フォーム |
|
△ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | |
| ファイバー |
|
× | ◯ | △ | ◎ | ◎ | ||
|
低 反 発 |
低反発ウレタン フォーム |
|
◎ | △ | ◎ | △ | △ | |
| 繊維わた |
|
◯ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ||
|
詰 め 物 次 第 |
ハイブリッド |
|
- | - | - | - | - | |
|
コ イ ル |
ボンネルコイル |
|
- | ◯ | △ | ◯ | △ | |
| ポケットコイル |
|
- | ◎ | ◎ | ◯ | △ | ||
| ※コイルスプリングマットレスの体圧分散性はコイルの上の詰めもの(ウレタンフォーム やわたなど)の量と品質により大きく左右され、単体での評価が不可能なため「 - 」としています。また、それぞれ加工・品質により△が◯になったり、◎が◯になることがあります。 |
通常、スプリングマットレスには、コイルスプリングの上にウレタンフォームなどの詰め物が使用されます。
高価なものほど高品質な詰め物が採用されます。
しかし、脚付きマットレスの多くは、この詰め物が少なすぎることが多々あります。
厚みにして1~2cm程度の量のものが大半です。

そのため、コイルスプリングの上に直接寝ているかのような、ゴリゴリっとした硬い寝心地のものが多くなっているのです。
もちろん、これには理由があります。
- 脚付きマットレスは2~3万円前後の安価なものとして販売される傾向があり、かけられる製造コストに限界があるため詰め物はコストカットされがちだから
- とはいえ、コストをかけて寝心地の良いものを作ろうとしても、販売価格で5~6万円前後になってしまい、ここまで高くなると消費者としても脚付きマットレスではなくベッドとマットレスを買い揃えるようになるため
- さらに、詰め物の品質を高めて寝心地が良くなったとしても、座り心地としてはやや柔らかくなりすぎてしまい好みが別れてしまうため
このように、寝心地が疎かになってしまいがちな構造が商品自体にあるのです。
その結果、前述したような、詰め物が少なくて硬すぎる脚付きマットレスばかりになってしまっているのです(もちろん、脚付きマットレスに限らず、安価なコイルスプリングマットレスにこの手のものは多いですが)。
2-2. 分割式(セパレート式)はフレームが腰に直撃する恐れがあるから
また、下記のイラストのような、分割可能なタイプはさらにおすすめできません。
| 一体型 | 分割型 | |
| 画像 |

|

|
| 寝心地 | ◯ | △ |
| 取扱い | △ | ◯ |
この仕様のものは脚付きマットレスを真ん中で分けて離すことができます。
そのため、移動させやすかったり椅子としても使いやすかったりと、生活をする上でのメリットが色々とあります。
が、肝心の寝心地が悪くなってしまいがちな落とし穴があります。

というのも、分割部分にフレームなどの硬い素材が仕込まれることがあるのですが、その硬い素材が腰に直撃する可能性があるからです。
これで腰を悪くする方もいるくらいですので、この点についてはよくよく考えるようにしてください。
2-3. おすすめできる脚付きマットレスとは
ここまで読み進めていただいた上で、「それでもどうしても脚付きマットレスがいいんだ」とお考えであれば、
- コイルスプリングの上の詰め物が5cm前後あるもの
- 分割式ではないもの
この2点を踏まえて選ぶようにしてください。
脚付きマットレスについて調べていると、腰を痛めるなどの評判を見聞きすることがあるかと思いますが、そのほとんどが上記2点を満たせられていないものだと私は考えています。
ただ正直、この2点を満たすものとなるとかなり限られます。
とはいえ、人生の1/3の時間を共にする家具ですので、厳しい目でしっかり選び抜いていただければと思います。
3. 他の選択肢と比べて、脚付きマットレスは何が劣る?
脚付きマットレスは、シンプルで省スペース・低価格という大きな魅力があります。しかし、フレーム付きベッドやすのこベッドと比較すると、耐久性や寝心地の面で見劣りする部分もあります。ここでは、主な比較項目ごとに違いを整理しました。
| 比較項目 | 脚付きマットレス | フレーム付きベッド/すのこベッド等 |
| 価格 | 安価 | 高額になりやすい |
| 通気性 | 一定の通気性はある | 通気性に優れ湿気対策に効果的 |
| 耐久性・寿命 | ローテーションできず劣化が早め | 長持ちしやすい |
| 寝心地・体圧分散 | 詰め物が少なく硬さを感じやすい | 厚みあるマットレスを選べるため体圧分散性が高い |
| 組み立て・手入れ | 軽量で設置は簡単だが陰干ししにくい | 重量はあるが分解や清掃がしやすくメンテナンス性が高い |
| 収納・付加機能 | ベッド下を収納に使える程度 | 引き出しやヘッドボードなど多機能モデルを選べる |
脚付きマットレスは「コストを抑えてシンプルに使いたい人」にはぴったりですが、長期的に使う耐久性や寝心地を重視するならフレーム付きベッドやすのこベッドの方が安心です。
特に腰痛対策や湿気対策を考える方は、脚付きだけで済ませず、他の選択肢も比較してみるのがおすすめです。
最後に
脚付きマットレスがなぜおすすめできないかについてご理解いただけましたでしょうか。
快適な寝心地のものを選ぶ一助になっていれば幸いです。
なお、もしマットレス選びのために情報収集中でしたら、ぜひ下記のページをご覧ください。自分にあったマットレスを選ぶための考え方の手順から、種類、素材、値段別におすすめマットレスを紹介しています。きっとお役立ていただけるはずです。
関連記事:快眠マットレスおすすめ11選&自分に合うものを絞り込む手順また、マットレスに関するページを以下にまとめましたので、気になるトピックがあればあわせてご参考にしてください。
■あわせて読んでおきたい「マットレス」の記事一覧
- 選び方編
○マットレスのおすすめ11選|専門家が教える自分に合うものを絞り込む手順
○敷布団とベッドマットレスの比較。素材ごとの併用の相性とおすすめ
○【失敗しないマットレスの選び方】硬さ、厚さ、密度、線材を吟味
○マットレスの3種類7素材を比較|特徴と選び方、おすすめできる人
○低反発と高反発の違い、あなたに合うマットレスはどっちか
○【快眠の方程式】マットレスの理想の硬さ=理想の寝姿勢
○マットレスの正しい厚み(高さ)は「用途と目的」を軸に考える
○【マットレスの通気性】素材・加工ベースで比較評価
- 使い方編
○【マットレスの使い方】シーツ、パッドの正しい順番とは
○マットレスにすのこは必要か?おすすめの選び方
○マットレスの上に布団を敷いてはいけない2つの理由と代替策
○マットレスの正しいダニ退治方法、二度と繁殖させない予防法
○マットレスのカビ除去方法と、再発を防ぐ予防対策
○ベッド・マットレスがずれる?それなら滑り止め対策を
○長生きでお得に!マットレスの寿命を判断する5つの目安
○賢い節約術!マットレスの処分方法を考えるべき順序
よくある質問
Q1. 脚付きマットレスの寿命はどれくらいですか?
A. 脚付きマットレスの寿命は、使用頻度や品質によりますが、一般的には約5〜8年が目安です。マットレス部分のウレタンやスプリングの劣化に加え、脚部のぐらつき・きしみなどが出てくるタイミングが買い替えのサインといえます。
とくにワンルームで毎日使用する場合や、体重が重めの方は、へたりや耐久性を意識して高密度・高反発素材のモデルを選ぶと長持ちしやすくなります。
Q2. 脚付きマットレスのギシギシ音が気になる場合の対処法は?
A. ギシギシ音の原因は、主にネジの緩み・フレームの接合部のきしみ・床との摩擦です。以下の対策で改善できることが多いです。
- ネジを定期的に締め直す
- 金属部の接触箇所に潤滑スプレーを使う(シリコン系)
- 脚の底にゴム製の防音マットやフェルトを貼る
また、床が平らでない場合や荷重が偏ると揺れやすくなるため、設置面を見直すのも効果的です。
Q3. 脚付きマットレスはカビやすいって本当?
A. 脚付きマットレスは床から離れている分、通気性がありカビが生えにくい構造です。ただし、「通気性が良いから絶対にカビない」というわけではありません。
以下のような状況ではカビが発生することもあります。
- 室内の湿度が高く、換気が不十分
- マットレスの底面にホコリがたまり湿気を吸う
- ベッド下に荷物を詰め込んで通気が妨げられている
定期的な換気や、除湿シート・除湿剤の併用、ベッド下の掃除などがカビ予防に有効です。
Q4. ベッドフレーム+マットレスと何が違うの?
A. 脚付きマットレスとベッドフレーム+マットレスの違いは、構造の柔軟性とカスタマイズ性にあります。
| 項目 | 脚付きマットレス | ベッドフレーム+マットレス |
| 一体型か分離型か | 一体型でシンプル | 分離型で自由に組み合わせ可能 |
| 移動・組み立て | 軽量・省スペース・組み立て簡単 | 重量あり・パーツが多い |
| 寝心地のカスタム性 | 限定的 | マットレスを自由に交換可能 |
| デザイン性 | ミニマル | 素材や色を選べてインテリアに合う |
| 寿命対応 | 全体を買い替える | マットレスだけ交換できる |
予算や部屋の広さ、メンテナンス性を考えて選ぶと後悔が少ないです。
著者紹介

著者情報
加賀 照虎(上級睡眠健康指導士)
上級睡眠健康指導士(第235号)。3,000万PV超の「快眠タイムズ」にて睡眠学に基づいた快眠・寝具情報を発信中。NHK「あさイチ」にてストレートネックを治す方法を紹介。取材依頼はこちらから。
各種SNSで情報発信中。
上級睡眠健康指導士(第235号)。3,000万PV超の「快眠タイムズ」にて睡眠学に基づいた快眠・寝具情報を発信中。NHK「あさイチ」にてストレートネックを治す方法を紹介。取材依頼はこちらから。
各種SNSで情報発信中。











「いくら眠っても眠い」
「寝付きが悪くなった」
など睡眠のお悩みを抱えてはいないでしょうか?
多くの研究データから質の低い睡眠は生活の質を下げることがわかっています。
快眠タイムズでは、皆さんの睡眠の質を向上させ、よりよい生活が送れるように、プロの視点から睡眠/寝具の情報を発信していきます。