竹シーツとは?効果や注意点、おすすめ商品を解説
更新日:
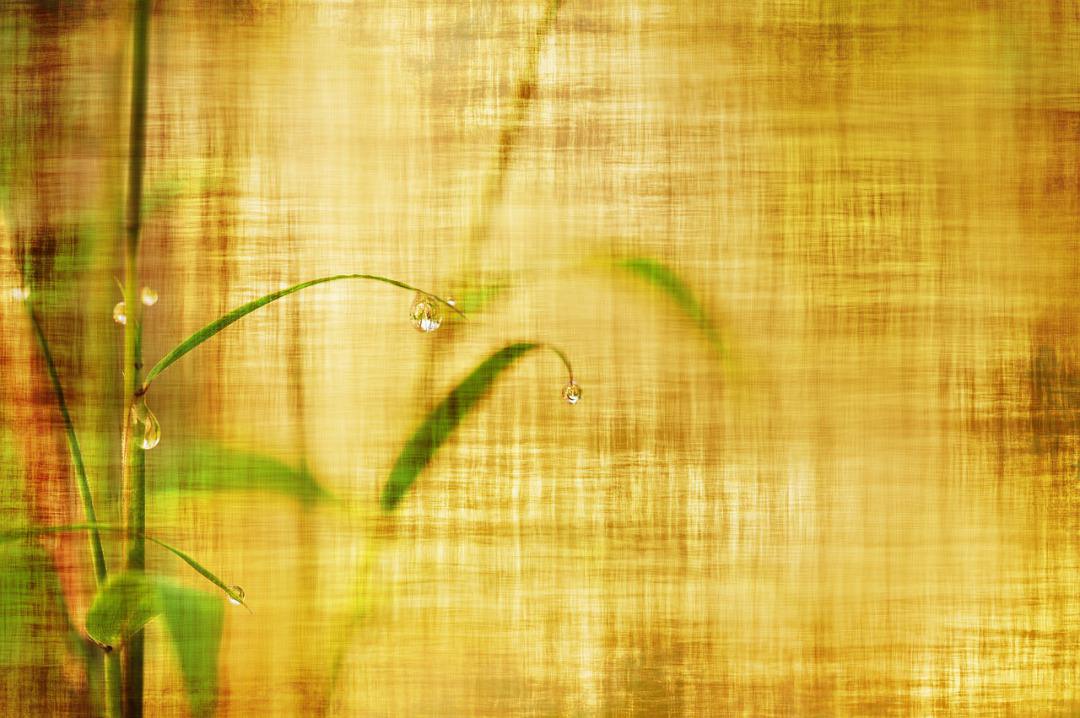
麻雀牌のような駒が連なっていたりゴザ形状になっていたりと、一見したところシーツに見えない竹シーツ。
過去の遺産のように見られがちですが、今でも夏になるとじわじわと人気のある商品です。とはいえ、あまり紹介されることがないため、詳しく知る機会も少ないと思います。
そこで本日は、
- 竹シーツの使用感(長所と短所)
- 竹シーツの注意点
- 竹シーツについてよくある質問
- おすすめの竹シーツ
などについて分かりやすく解説していきます。
1. 竹シーツとは?
竹シーツとは、天然素材を利用した夏用寝具で、熱伝導率と通気性に優れているのが特徴です。竹を細かく加工して編み込むことで、敷くだけでひんやりとした触感が得られ、暑い季節の寝苦しさを和らげます。
一般的な布製のシーツと比べて放熱性が高いため、体温がこもりにくく、寝返りを打つたびに清涼感を感じやすい点が魅力です。また、竹は湿気を吸収・放出しやすい性質があるため、蒸れを抑え、さらりとした寝心地を保ちます。
2. 竹シーツの特徴と使用感
駒形状やゴザ形状など竹シーツにはありますが使用感はほぼ似たり寄ったりです。細かい違いについては後述しますが、まずは全体としての使用感をご紹介します。
| 長所 | 短所 |
|
|
2-1. 竹シーツの長所(メリット)
2-1-1. ひんやり感がある
表面がツルツルに磨かれているので熱伝導率が非常に高く、皮膚が触れた瞬間に熱を奪うのでヒヤッとした冷たさを感じられます。
2-1-2. 熱の発散性がある
竹は内部構造が素晴らしく、多孔質の細かい繊維で構成されているので体から奪った熱が内部に溜まりにくく素早く発散されます。
2-1-3. 通気性もある
その竹をチップ状・棒状に加工し小さなスペースを空けて配置することで通気性が確保されています。これにより、ひんやり感が長く感じられることにもなります。
2-2. 竹シーツの短所(デメリット)
2-2-1. 肌当たりはやや硬い
竹シーツは言うなればむき出しの木のチップの上で寝るようなものなので、硬く感じられます。特に、痩せ気味の方や骨張っている体格の方には、ゴリゴリとした不快感が強く感じられるのであまりおすすめ出来ません。
2-2-2. ペタつき感がある
寝汗が多い方だと、ツルツルとした表面が汗でペタペタと密着するような肌感になるので好みが分かれます。
2-2-3. トゲ、ささくれがあることも
個々の製品にもよりますが竹の繊維がトゲのように飛び出ていて刺さることもあります(この対策は後述します)。

2-3. 竹シーツの注意点
とても良い製品ですが、何気なく選んだり使ったりしてしまうと思わぬ失敗をしてしまうことがあるので、以下3つの点にご注意ください。
2-3-1. プラスチック製は非推奨
竹駒シーツに似た製品でプラスチック製の駒のシーツがあります。こちらも瞬間的なひんやり感があり快適なのですが、竹のような天然の熱発散性はありません。そのため、ひんやり感を求めて購入するのなら竹製のものを購入することをおすすめします。
2-3-2. 髪の毛を挟まないように
チップ形状もゴザ形状のどちらも竹同士に微妙な隙間があります。そのため、寝ている間に髪の毛がこの間に入り込み絡まることがあります。
寝相でゴロゴロと動く時や、起床時に起き上がる時に、髪の毛が引っかかって痛い思いをする場合があります。特に髪の毛の長い方、パーマをかけている方に起こりやすいです。気になるようでしたら枕の下にタオルを敷くなどして、髪の毛が竹シーツに入り込まないように対策を取りましょう。
2-3-3. 使用前にトゲの確認を
トゲの発生率は各製品の質に大きく左右されますが、天然製品ですので絶対にトゲがないとは言い切れません。そのため、購入したら使用前に乾いたタオルで繊維の流れに沿ってしっかり拭きましょう。もし繊維が飛び出ていたらタオルに引っかかり取り除くことができます。手を怪我しないように注意しながら行ってください。
3. 竹シーツと他の冷感寝具との違い
夏に人気の冷感寝具には、接触冷感パッドやジェルマット、い草シーツなどさまざまなタイプがあります。それぞれに特徴がありますが、竹シーツは天然素材ならではの通気性と熱伝導性による持続的な涼しさが大きな魅力です。
ここでは、竹シーツと他の冷感寝具の違いを比べながら解説します。
3-1. 竹シーツと接触冷感パッドの違い
接触冷感パッドは、熱伝導率の高い化学繊維を利用し、触れた瞬間にひんやり感を得られるのが特徴です。ただし、体温でぬるくなりやすく、冷房や扇風機と併用するのが前提です。
これに対して竹シーツは、竹の表面が熱を逃しやすいため、寝返りを打つたびに冷たさが回復しやすく、自然な涼しさが持続します。
3-2. 竹シーツと冷感ジェルマットの違い
冷感ジェルマットはジェル素材による強い冷却感が魅力で、首や背中など局所的に冷やすのに便利です。ただし、敷きっぱなしにすると湿気がこもりやすく、寝心地が重く感じられることもあります。
竹シーツはジェルのような強烈な冷たさはありませんが、通気性と放熱性によって全体をバランスよく冷やします。
3-3. 竹シーツとい草シーツの違い
い草シーツは吸湿性や消臭性に優れ、持ち運びもしやすい点が特徴です。
ただし、硬さが気になる人もおり、長時間の睡眠では寝心地に影響することがあります。竹シーツは同じ天然素材でも、熱伝導性による冷却感と寝心地のバランスで差別化できます。
4. 竹シーツを選ぶときのチェックポイント
竹シーツにはいくつかのタイプやサイズがあり、選び方次第で寝心地や扱いやすさが大きく変わります。ここでは購入前に押さえておきたいポイントを解説します。
4-1. 駒形状とゴザ形状の違い
竹シーツは大きく「駒形状」と「ゴザ形状」に分けられます。駒形状は竹を細かくカットして並べたもので、ひんやり感が強い反面、表面の硬さを感じやすい傾向があります。
ゴザ形状は竹を細く割いて編み込んだもので、硬さがやわらぎ肌あたりが優しい反面、冷感はややマイルドです。なかには竹の繊維がささくれ立ちやすい製品もあるため、仕上げの丁寧さを確認すると安心です。
4-2. サイズ選び
竹シーツにはシングルやダブルだけでなく、セミシングルやハーフなど多様なサイズがあります。ベッドサイズに合わせるのが基本ですが、汗や蒸れが気になる部分だけに敷きたい場合はハーフサイズも便利です。
特に狭い部屋や収納スペースの限られた環境では、扱いやすいサイズを選ぶことで後悔を防げます。
4-3. 湿気対策のしやすさ
竹は通気性に優れていますが、床に直置きすると湿気がこもり、カビやダニの原因になりかねません。除湿シートや、すのこと併用すれば空気が循環しやすくなり、日常的な湿気対策が簡単になります。
さらに、軽量で干しやすいタイプを選ぶと、ローテーション干しや陰干しも手軽にでき、清潔に保ちやすくなります。
5. おすすめの竹シーツ

- 製品:竹シーツ 駒形状
- 価格:5,980円
- 【当製品の販売ページ】
駒形状の竹シーツです。ツルッと磨いた表面の上に蜜蝋を塗ることで肌当たりをさらに良くしています。体感温度を3℃も下げるほどのひんやり感があります。また、駒同士を伸縮性のあるナイロンで結合していることにより、個々の柔軟性が生まれ体のラインにフィットしやすいよう工夫が施されています。

- 製品:竹シーツ ゴザ形状
- 価格:4,990円
- 【当製品の販売ページ】
ゴザ形状のため上記のものよりも柔らかな寝心地が期待できます。その半面、ひんやり感は多少劣りますが、それでも体感温度を0.7℃下げるほどの冷感があります。そのため、「竹シーツは興味あるけど硬いと聞いているから少し敬遠している」という方におすすめです。

- 製品:い草寝ござシーツ
- 価格:2,980円
- (販売終了の模様)
「上記のゴザ形状の竹シーツでも多少硬そう」と感じる方には、竹シーツではなく「い草のシーツ」も選択肢として一考することもおすすめします。竹シーツのような冷感こそありませんが、天然の調湿力、通気性で涼やかに眠れます。また、消臭効果もあるので寝汗が多い方に向いています。

- 製品:い草マット
- 価格:5,481円
- 【当製品の販売ページ】
上記の製品の3cmマットタイプです。「どうせなら寝心地も良くなるようなシーツがあればな」とお考えの方におすすめします。3cmのウレタンフォームが内部に詰められているので、い草の使用感と共に寝心地改善も期待できます。
6. 竹シーツについてよくある質問
それでは次に、竹シーツの購入に際してよくある疑問に関してご紹介します。
6-1. 竹シーツのお手入れ方法
竹シーツは洗濯機で洗うことができません。また、天然物なのでシーズンオフ時の保管方法にも特別の配慮をする必要があります。
6-1-1. 竹シーツの洗い方
硬く絞ったタオルでしっかりと拭き掃除をしましょう。パジャマを着用せずに使用される場合、寝汗以外にも皮脂が竹シーツに付きます。皮脂は汗よりも頑固な汚れになりますので、寝苦しい夜が続く時期は少なくとも週に1度は拭き掃除をするようにしましょう。
6-1-2. 竹特有の臭いが気になる
購入当初は竹と加工剤の匂いが混じったツンとした匂いがすることがあります。匂いに敏感な方は不快なため返品を考えることもあると思いますが、屋外で数日空気に晒しておくと大分軽減されますので一度お試しください。
6-1-3. 収納方法
シーズンオフに押入れにしまう時、湿気に注意してください。押入れ内の湿気が高いと竹にカビが生えてしまうことがあります。押入れから湿気を取り除くことも大切ですが、以下の2点も同時に行いましょう。
- 竹シーツを日干ししてからしまう
- 竹シーツを新聞紙で包んでしまう
そうしていただければカビ発生の可能性を大きく減らすことができます。
6-1-4. ダニ退治の方法
いくら通気性の良い竹シーツといえど、寝室が高温多湿の環境だとダニが発生することがあります。
その場合、まずは徹底的に天日干しをして乾燥させましょう。ダニは乾燥した環境を好まないので追い払うことができます。炎天下であれば熱の力で退治することも期待できるので、天日干しの後はダニの死骸を掃除機でしっかりと吸い取りましょう。
(※もし、ダニの発生源が布団・マットレスの可能性があれば、こちらのページ『布団のダニを退治する11の方法と再発防止3ステップ【専門家監修】』で11通りのダニ退治方法を比較した上で、効果的でおすすめな方法を紹介しているのであわせてご参考にしてください。)
6-2. 駒形状とゴザ形状どちらがいいのか?
竹シーツを選ぶ時、以下でご紹介する駒形状のものとゴザ形状のものを見ると思います。どちらも一長一短なのですが、
- 駒形状:ひんやり感は強いが硬さが目立つ
- ゴザ形状:硬さは軽減されるがひんやり感は若干程度に。ものによってはトゲが目立つ。
などの違いがあります。あなたが重視する点を基準に選ぶと良いと思います。詳しくは5章のおすすめのものをご覧ください。
6-3. 竹シーツはジェルマットと比べてどうなのか?
夏のひんやりシーツには、竹シーツ以外にもジェルマットもあります。
そのため、「どちらが良いんだろう」と迷われることもあると思いますが、竹シーツをおすすめします。ジェルマットには通気性がないことが多いため、どうしても熱が溜まりやすくひんやり感の持続性に欠けるからです。
6-4. 竹シーツはエアコンと併用すると効果は高まりますか?
はい、エアコンと併用するとさらに効果が高まります。竹は熱伝導率が高く、表面のひんやり感を持続しやすい素材です。
冷房で室温を下げると通気性が向上し、蒸れや寝汗を抑える効果が強まります。節電しながら快適な寝心地を得たい方におすすめです。
6-5. 竹シーツは冬に使えますか?
冬場は保温性が低いため基本的には向いていません。天然素材の特性として熱を逃がしやすく、寒い季節には冷たすぎて寝心地が悪化することがあります。
冬は布団や毛布との組み合わせよりも、い草や布製のベッドパッドに切り替える方が適しています。
6-6. 竹シーツは子供や高齢者でも安心して使えますか?
A:基本的には安心して使えますが、注意点があります。表面の硬さや凹凸が敏感肌の方には刺激となる場合があり、特に小さなお子様や高齢者は体圧が集中して寝心地が悪くなる可能性があります。
通気性と蒸れにくさは魅力ですが、心配な場合はジェルマットや柔らかい素材との併用を検討してください。
6-7. 竹シーツの寿命はどのくらいですか?
使用頻度やお手入れによりますが、耐久性は3〜5年程度が目安です。天然素材のため湿気対策を怠るとカビや割れの原因になり、寿命が短くなります。
定期的に陰干しをして通気性を保てば、長期間ひんやり感を楽しむことができます。
最後に
竹シーツの魅力が伝わっていると幸いです。
しかし、もしあなたが「硬い使用感はあまり好きではない」とお考えなら、こちらのページ『接触冷感敷きパッドの選び方とおすすめ5選【冷たくて蒸れにくい】』でおすすめの冷感敷きパッドを紹介しているので、あわせてご参考にしてください。
著者紹介

著者情報
加賀 照虎(上級睡眠健康指導士)
上級睡眠健康指導士(第235号)。3,000万PV超の「快眠タイムズ」にて睡眠学に基づいた快眠・寝具情報を発信中。NHK「あさイチ」にてストレートネックを治す方法を紹介。取材依頼はこちらから。
各種SNSで情報発信中。
上級睡眠健康指導士(第235号)。3,000万PV超の「快眠タイムズ」にて睡眠学に基づいた快眠・寝具情報を発信中。NHK「あさイチ」にてストレートネックを治す方法を紹介。取材依頼はこちらから。
各種SNSで情報発信中。













「いくら眠っても眠い」
「寝付きが悪くなった」
など睡眠のお悩みを抱えてはいないでしょうか?
多くの研究データから質の低い睡眠は生活の質を下げることがわかっています。
快眠タイムズでは、皆さんの睡眠の質を向上させ、よりよい生活が送れるように、プロの視点から睡眠/寝具の情報を発信していきます。