【熟睡敷布団のおすすめ9選】正しい選び方3つのコツ
更新日:

敷布団は本当にさまざまです。
どれを選ぶべきなのか途方に暮れてはいないでしょうか?
私自身、寝具を作っている立場ということもあり「どの敷布団が一番いいの?」と聞かれることがあります。しかし、これは回答が非常に難しい質問です。
というのも、寝心地の好み、体型、生活環境など人それぞれ10人10通りのため、ある人に合うものがある人には合わないことが往々にしてあるからです。
そこで本日は、
- 切り口(サポート性/蒸れにくさ/手入れ)別の選び方
- 床置きかベッド利用かの判断の目安
- おすすめの敷布団
- 敷布団によくある疑問点
などについて説明します。
敷布団選びの参考にご活用ください。
1. 敷布団とマットレスの違いは?どちらがおすすめ?
敷布団とマットレスは、どちらも身体を下から支える大切な寝具ですが、厚みや構造、使う場所、お手入れの方法などに大きな違いがあります。この記事では、それぞれの特徴やメリット・デメリットをわかりやすく比較しながら、ライフスタイルや寝る環境に合わせた選び方を紹介します。
1-1. 敷布団の特徴と役割
敷布団には、寝ているあいだに身体の一部に体圧が集中するのを防ぎ、無理のない寝姿勢をキープする役割があります。体全体をバランスよく支えることで、肩や腰への負担をやわらげ、快適な眠りをサポートしてくれます。
また、一口に敷布団といっても素材によって特徴は異なります。たとえばウールわたの敷布団は保温性や吸放湿性に優れ、適度な弾力性も持ち合わせています。
一方でポリエステルわたの敷布団は軽量でダニ防止などの加工がしやすく、価格も比較的手頃なのが魅力です。さらに敷布団は、日本の住まいに馴染み深い存在で、畳やフローリングに直接敷いて使えるのも特徴です。
マットレスに比べて薄く軽量で、折りたたんで収納できるため、毎日の布団の上げ下ろしがラク。ワンルーム暮らしや来客用にも適しています。
1-1-1. 敷布団のメリットとデメリット
敷布団は種類や素材が豊富で価格帯も広く、生活スタイルに合わせて選びやすい寝具です。吸湿性に優れたウールタイプ、厚みがしっかりあるボリュームタイプ、省スペースで扱いやすい軽量タイプなど、目的に応じて選べます。
軽く持ち運びやすい点や、畳やフローリングにそのまま敷ける点も大きなメリットです。一方で、マットレスに比べて耐久性はやや短く、3~5年程度でへたりや底つきが出やすい傾向があります。
快適さを保つためには、天日干しで湿気を逃がしたり、掃除機でダニ対策をするなど、定期的なお手入れが欠かせない点がデメリットといえるでしょう。
1-2. マットレスの特徴と役割
マットレスは、主にベッドフレームの上に敷くことを前提に作られた寝具です。厚みがあり、コイル・ウレタン・ファイバーなどを使った構造で、弾力性を備えているのが特徴。
体の重心が一箇所に集中するのを防ぎ、腰や背中への負担をやわらげます。種類ごとに高反発・低反発などの特性があり、いずれも体圧分散に優れているため快適な寝姿勢をサポートしてくれます。
特に腰や肩への負担軽減を重視する方には、マットレスを選ぶメリットが大きいでしょう。最近では、ベッドだけでなく床に直接敷ける三つ折りタイプのウレタンマットレスも人気です。折りたためて収納できるので、一人暮らしや来客用としても活用しやすく、ライフスタイルに合わせて選べる幅が広がっています。
1-2-1. マットレスのメリットとデメリット
ウレタンマットレスは、複雑なカット加工が可能なため体圧分散性や寝姿勢保持に優れています。さらに耐用年数が長く、ホコリが出にくいため、清潔に使いやすいのも魅力です。
ただし、ウレタン素材は蒸れやすい傾向があり、通気性を考慮した製品を選ばないと快適さが損なわれることも。湿気がこもるとカビやへたりの原因になるため、除湿シートを敷いたり、使用後に立て掛けて風通しを良くするなどの工夫が必要です。
敷布団ほど頻繁に天日干しをする必要はありませんが、湿気対策は欠かせません。耐久性や使いやすさに優れる一方で、湿気対策がポイントとなる寝具です。
1-3. 敷布団とマットレスの違い
敷布団とマットレスは、どちらも体を下から支える寝具ですが、厚み・構造・収納性・耐久性などに明確な違いがあります。ライフスタイルや寝心地の好みによって、どちらが合うかは大きく変わってきます。以下の表で違いを整理しました。
| 項目 | 敷布団 | マットレス |
| 厚み・構造 |
|
|
| 使う場所 |
|
|
| 寝心地 |
|
|
| 収納性 |
|
|
| 耐久性 |
|
|
| おすすめの人 |
|
|
敷布団かマットレスかは、自分の体格や部屋の広さ、使うシーンに合わせて選ぶことが大切です。
1-4. 敷布団とマットレスはどちらがおすすめ?
結論として、敷布団とマットレスのどちらが良いかは寝る場所やライフスタイルによって異なります。
1-4-1. 敷布団がおすすめなケース
- 畳の上で眠りたい
- 布団を毎日上げ下ろしして収納したい
- ワンルームや限られたスペースで暮らしている
- 来客用として簡単に用意したい
- 手頃な価格で寝具をそろえたい
1-4-2. マットレスがおすすめなケース
- ベッドフレームを使って寝たい
- フローリングで直接寝たい
- 長時間眠っても体に負担をかけたくない
- 腰の沈み込みや底つき感が気になる
- 寝返りが打ちやすく、しっかり支えてくれる寝具を探している
敷布団とマットレスは、それぞれにメリットがあり、どちらが優れているかは一概に決められません。収納性や手軽さを重視するなら敷布団、寝心地や体へのサポートを重視するならマットレスがおすすめです。自分の住環境やライフスタイルに合わせて、最適な寝具を選びましょう。
2. 敷布団選びの3つのコツ
敷布団を選ぶとき、以下の3つの切り口から考えましょう。
- 腰・背中の寝心地にこだわるなら、サポート性を重視する
- 蒸れにくい寝心地にこだわるなら、吸放湿性を重視する
- 使い勝手にうんざりしているなら、使いやすさを重視する
これらの中からあなたが重視するのはどれでしょうか?
そのポイントを押さえつつ敷布団を選びましょう。
そしてその次に、適切なサイズなどについて考えるようにしましょう。
2-1. 腰のサポート性を重視した選び方
一般的な敷布団は薄くて弾力性に欠けるものが多いです。
そのため、底つき感に悩まされることが多々あります。
できるだけ厚さとサポート性のあるものを選ぶようにしましょう。
| 底つき感のイメージ | |
| 仰向け |  |
| 横向き |  |
敷布団の厚みはあなたの体重をもとに考えましょう。
そうでないと腰を痛めてしまいます。
| 使用者の体重 | 必要最低限の厚さ | |
| ウレタンフォーム | ファイバー | |
| 30kg | 5cm | 3cm |
| 60kg | 7cm | 5cm |
| 80kg | 10cm | 7cm |
| 100kg | 13cm | 10cm |
ただ、ここで注意点が1つあります。
素材によってサポート力が変わる点です。
| イメージ | 体圧分散 | 反発弾性 | 吸湿性 | 放湿性 | 洗濯耐性 | 重量目安 | |
| 木綿 (綿/コットン) |
 |
◯ | ◯ | ◎ | △ | △ | 6kg |
| ポリ エステル |
 |
◯ | ◯ | △ | - | ◯ | 3.5kg |
| 羊毛 (ウール) |
 |
◯ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 3.5kg |
| キャメル (らくだ) |
 |
◯ | ◯ | ◎ | ◎ | △ | 3kg |
| 真綿 (絹/シルク) |
 |
◯ | ◯ | ◎ | ◯ | △ | 3kg |
| ウレタン フォーム |
 |
◯ | ◎ | △ | - | △ | 6kg |
(重さはシングルサイズのものの目安です。)
例えば、真綿の敷布団の厚み10cmと、ウレタン敷布団の厚み10cmではサポート性がまったく違ってきます。
このような理由から、腰・背中のサポート性を重視する方におすすめできる敷布団は以下のようなものになります。
- ポリエステル固わた入りの敷布団
- ウレタン入りの敷布団
- ウレタン素材の敷布団
- アンダーマットレスと敷布団の組み合わせ
もしあなたが腰に疲れや痛みを抱えているのなら、是非これらを目安に選ぶようにしてください。
具体的な商品については2章でご紹介しています。
2-2. 蒸れにくさ重視の素材の吸放湿性を重視した選び方
眠るとき、人の体温は下がります。
体温を下げることで、脳と体を休められるのです。

だから、寝具の吸放湿性が大事なのです。
蒸れない睡眠環境にすることで体温調整ができ、快適に眠れるようになります。
そこでこだわってもらいのが素材です。
| 素材 | 肌触り | 吸水性 | 放湿性 | 洗濯 | 費用 | |
| 綿(コットン) |  |
◯ | ◎ | △ | ◯ | 中 |
| ポリエステル |  |
◯ | △ | - | ◎ | 低 |
| レーヨン |  |
◯ | ◎ | ◯ | △ | 中 |
| 麻(リネン) |  |
△ | ◎ | ◎ | ◯ | 高 |
側生地と中わた、どちらも吸放湿性の高いものを選びましょう。
例えば、羊毛やキャメル、シルクなどです。
コットンは吸水性は高いものの放湿性が低く乾きにくいため、干すのに時間がかかる欠点があります。
とはいえ、羊毛やキャメルなどは高価なため薄いものが多いです。
そのため、アンダーマットレスと羊毛敷布団などのように組み合わせることをおすすめします(かなり高価にはなりますが)。
2-3. 手入れを楽にするための選び方
敷布団の最大の欠点が「手入れの手間」です。
毎日押し入れから出し入れしなければなりませんし、週に2~3回は干さなければなりません。そうでないと湿気って寝心地が悪くなりますし、最悪、ダニやカビが繁殖することになります。
| ダニ・カビ繁殖三大原因 | 発生源 | |
| 温度 |  |
|
| 湿度 |  |
|
| エサ |  |
|
ただ、かなり面倒ですよね。
「そんなまめにお手入れできない」
このようにお考えでしたら、以下のような敷布団選びがおすすめです。
- ウレタン素材の敷布団
- アンダーマットレスと軽量敷布団の組み合わせ
厚みが10cm前後のウレタン素材の敷布団であれば、壁に立てかけるだけで干す作業が完了します。
お手入れがすごく楽になります。

「どうしても敷布団がいいんだ」
このようにお考えの方は、アンダーマットレスに軽量敷布団を組み合わせましょう。
軽量敷布団は2~3kgくらいですので手入れの手間こそかかりますが、軽いため簡単に行えます。
2-4. 適切なサイズの選び方
敷布団のサイズ選びは要注意です。
一般的に下記のようなサイズと用途とされています。
| 名称 | 幅寸法 | イメージ | 寝室目安 | 用途 |
| セミシングル | 80cm |  |
4畳 | 1人(子供・小柄な方) |
| シングル | 97cm |  |
4畳 | 1人(中柄な方) |
| セミダブル | 120cm |  |
6畳 | 1人(大柄な方) |
| ダブル | 140cm |  |
8畳 | 1~2人(小柄な方2人) |
| クイーン | 160cm |  |
8畳 | 2人(中柄な方) |
| キング | 180cm |  |
10畳 | 2人(大柄な方) |
一人寝であればシングルもしくはセミダブルを選べば良いでしょう。
これについて相違はありません。
問題は二人寝用です。
結論から言うと、二人寝用ならシングル二枚がおすすめです。
まずダブルサイズは二人寝で寝るには狭すぎます。


寝返りなどがしづらいです。
寝づらくなるので二人寝でダブルはやめましょう。
そしてクイーンサイズは二人寝用のサイズとしてはいいのですが、敷布団が大きく重たくなるため手入れが大変なのでおすすめできません。
そのため、二人寝用ならシングル二枚がおすすめということなのです。
3. おすすめの熟睡できる敷布団9選
次に、おすすめの敷布団を紹介していきます。
3-1. エコラテ エリート 三つ折り敷布団型マットレス

- 製品:エコラテ エリート 三つ折り敷布団型マットレス
- 価格:19,990円
- 【商品ページはこちら】
敷布団型マットレスです。
3万円前後の予算で考えている人におすすめです。反発弾性45%の柔軟な寝心地に加えて、凸凹プロファイル加工で適度な体圧分散性になっています。
厚みが10cmになっているため、敷布団のようにコンパクトに折りたたんで押入れに収納できます。敷布団の手軽さと、マットレスの寝心地を兼ね備えた仕上がりになっています。
無駄を削ぎ落として最高のコストパフォーマンスを目指しました。自社製品なので恐縮ですが、まさに優秀(エリート)な自信作です。ただいま「60日トライアル返品無料プログラム」を設けています。この機会をお見逃しないようご利用ください。
3-2. セルプール ハイブリッドマットレス

- 製品:セルプールハイブリッドマットレス
- 価格:39,000円
- サイズ:98×197×8cm
- 【商品ページはこちら】 / 【セルプール紹介ページはこちら】
トップクラスの弾力性(反発弾性63%)を持った敷布団型ウレタンマットレスです。
厚みがたった8cmの薄型マットレスですが、ウレタン密度が50Dとずば抜けて高いので、見かけによらずしっかりと体をサポートします。また、ウレタンフォームが吸放湿するため、ウレタンマットレスなのにムレにくいという素晴らしい性能を持っています。自社製品で手前味噌ですが、心から惚れ惚れする寝心地です。
3-3. 木綿敷布団

- 製品:木綿敷布団
- 価格:11,691円
- 【販売ページ@楽天】
木綿敷布団は、昔ながらの寝心地が好みの方にうってつけです。
中央がやや盛り上がるように仕立て上げられ、分厚いながらも腰が落ち込みにくく寝姿勢を悪くしないよう工夫が凝らされているのも手作りだからこその味わいです。ただ、木綿は汗の吸収にすぐれるものの、渇きにくい欠点があるため、きちんとこまめに干すことを怠らないようにしましょう。
3-4. 洗濯機で洗える軽量敷布団

- 製品:洗濯機で洗える軽量敷布団
- 価格:7,490円
- 【販売ページ@ベルメゾン】
丸ごと洗濯機に突っ込んで洗える敷布団です。キレイ好きの方におすすめです。
中わたが0.6kgと軽量なので、洗うのも干すのも手間がかからずとても楽に行なえます。薄めなため体の大きい人だと底つき感がある可能性もあります。やや硬めの敷布団やトッパーと組み合わせて使うとよいです。
3-5. アラエマックス

- 製品:アラエマックス
- 価格:15,999円
- 【販売ページ@楽天】
こちらも洗える敷布団です。
丸ごと洗えるわけではないのですが、ポリエステルわた+ポリエステル固わた+ポリエステルわたの3層構造になっておりそれぞれを分割することのできため、一番上の汚れやすいところだけを簡単に洗える設計になっています。洗える敷布団で寝心地がしっかりしているものをお探しの方におすすめです。
3-6. 西川 体圧分散羊毛棍敷き布団

- 製品:西川 体圧分散 プロファイル固わた羊毛棍敷布団
- 価格:12,300円
- 【販売ページ@楽天】
わた+固わた+わたの3層構造になっている敷布団です。
固わたが入っているのでフローリングの上にこれ1枚だけでも底つき感少なく寝られるしっかりとした作りになっています。また、羊毛わたをブレンドしているので、体圧分散性にすぐれていますし、弾力性のある気持ちいい寝心地です。
3-7. 西川ムアツ敷布団ベーシック

- 製品:西川 ムアツ敷布団
- 価格:23,900円
- 【販売ページ@楽天】
ポリウレタンフォームの敷布団です。
しっかりと体を支えるクッション性はやはりウレタンフォームが頭一つ抜きん出ています。また、ウレタンフォームの表面に凸凹のプロファイルカットが施されているため、体圧分散性と通気性が良くなっています。重量も4.7kgと敷布団としては手軽に持ち上げられる重さです。
3-8. ビラベック 羊毛敷布団

- 製品:ビラベック 羊毛敷布団
- 価格:59,400円
- 【販売ページ@楽天】
羊毛ベッドパッドを世界で初めて作った会社の羊毛敷布団です。
木綿わたやポリエステルわたにはない、独特な弾力性が気持ちいです。また、羊毛にコーティングやヒダをそぎ落とすなどの加工を施していないため、羊毛本来の調湿機能が失われていなく快適に寝られます。ただ、体の大きい方にはこれ1枚だけだとサポート性に若干難があるかもしれません。
3-9. イワタ キャメル敷布団

- 製品:イワタ キャメル敷布団
- 価格:72,360円
- 【販売ページ@楽天】
特別洗浄が施されたキャメルの毛が使われた敷布団です。
羊毛と同じく弾性に富んだ気持ちい寝心地です。さらに、キャメルの毛も保温性・吸放湿にすぐれるので、暖かいのにムレにくく快適に寝られます。ただ、こちらも羊毛敷布団と同じく、何かしらしっかりめの敷布団やトッパーの上に重ねて敷いて寝られると、より底つき感なく寝られます。
4. 敷布団の使い方の目安
あなたに合う敷布団は見つかりましたか?
次に、敷布団をどう使うかについて解説します。
4-1. 床置きかベッド利用か
敷布団は床に敷いて使うものです。
しかし、ベッドの上で使うことも可能といえば可能です。
それぞれ以下のようなメリット・デメリットがあります。
| 床置き | ベッドの上 | |
| 省スペース |
◎ |
△ |
| 湿気対策 |
△ |
◯ |
| ハウスダスト |
△ |
◯ |
| 床冷え |
△ |
◯ |
| 費用 |
◯ |
△ |
睡眠環境のことを考えるとベッドの上で寝るほうが良いですが、スペース性や費用のことを考えると床置きも捨て難いです。
あなたの生活スタイルに合うほうを選びましょう。
なお、ベッドの床板が畳になっているものだと、ベッドの上でも違和感少なく敷布団が使えるのでおすすめです。
| すのこ | 畳 | 張り板 | |
| 画像 |  |
 |
 |
| 素材 | スチールor木材 | 木材 | 木材 |
| クッション性 | △ | ◯ | △ |
| 調湿性 | △ | ◯ | △ |
| 通気性 | ◯ | △ | △ |
| 耐久性 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 価格 | ふつう | 安い | 安め |
4-2. シーツやパッドの組み合わせ方法
敷布団にそのまま寝るのはやめましょう。
シーツやパッドなどを上手に組み合わせましょう。
| 敷きパッド | ベッドパッド | ベッドシーツ | トッパー | プロテクター | |
| 画像 |  |
 |
 |
 |
 |
| 役割 |
|
|
|
|
|
| 厚み | 1~2cm前後 | 3~4cm前後 | 5mm前後 | 3~5cm | 5mm前後 |
| 温湿度調整 | ◎ | ◎ | ◯ | × | △ |
| 汚れ防止 | ◯ | ◯ | △ | △ | ◎ |
| 洗濯 | △ | △ | ◯ | × | ◯ |
| 体圧分散性 | △ | ◯ | × | ◎ | × |
とはいえ、全て使う必要はありません。
おすすめの使い方を紹介します。
-
【敷布団→敷きパッド】
最低限の組み合わせです。シーツだけ敷かれる方がいますが、シーツだけでは汚れを防ぎきれません。何か一枚だけ敷くなら敷きパッドがおすすめです。敷きパッドは週に1度ほど洗い替えしましょう。 -
【敷布団→敷きパッド→シーツ】
敷きパッドだけ敷いていると洗濯が大変です。そのため、余裕があればその上にさらにシーツを敷くことをおすすめします。この場合、シーツを週に1~2回洗って、敷きパッドは2~3ヶ月に1回洗っていただけば結構です。
5. 敷布団選びによくあるQ&A
敷布団ユーザーによくある疑問です。
一度目を通しておきましょう。
5-1. 打ち直しは可能か?
基本的に打ち直しは、木綿敷布団しかできません。
お店によっては羊毛も対応可能なところがなくはないですが少ないです。
打ち直しの料金など詳しくはこちらのページ『布団の打ち直し価格の相場、考えるべきポイント』で解説しているので参考にしてください。
5-2. 敷布団はダニが繁殖しやすい?
繊維わたはダニの住処になりやすいです。
特に、天然繊維や湿気りやすい素材だと、ダニが繁殖しやすいです。
素材ごとにランク付けをするなら、木綿>羊毛>キャメル>ポリエステル>ウレタンの順番です。ダニが気にならなら、洗える敷布団や、ウレタン敷布団がおすすめです。
5-3. 湿気・カビ対策には何をすればいいのか?
以下のお手入れを怠らないようにしましょう。
- 敷布団を敷きっぱなしにしない
- 敷布団は週に2~3回干す
- ウレタン敷布団なら週に1~2回は壁に立てかける
- 除湿シートを敷布団の下に敷く
- 敷きパッドを敷布団の上に敷く
あなたのご家庭の環境にもよりますが、湿気が強いのであれば尚更注意するようにしましょう。
5-4. フローリングに直に敷布団でも大丈夫?
大問題というほどではありませんが、フローリングの上で敷布団を使っていると、
- 敷布団が湿気りやすい
- 底つき感がでやすい
などに悩まされることも少なくはないです。
もしあなたが気になるのなら、湿気対策に除湿シート、底つき感対策に薄めのトッパーやコルクマットなどを活用するとよいでしょう。
5-5. 冬の底冷え(床冷え)対策には何をしたらいい?
木造の一軒家に住んでいると、布団の下から伝わる冷気で凍えますよね。
敷布団の下にコルクマットやカーペット(絨毯など)を敷きましょう。安い割にはけっこう効果があるのでおすすめです。
| フローリング | 畳 | 除湿シート | 床置きすのこ | すのこベッド | コルクマット | アルミシート | |
| 画像 | |||||||
| 吸湿性 | △ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
| 通気性 | △ | △ | △ | ◯ | ◎ | △ | △ |
| 保温性 | △ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◎ |
| クッション性 | △ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
アルミシートは保温性こそ高いものの、床と敷布団の間に入れるとその上下の温度差により結露が一層ひどくなることがあります。
そのため、布団の結露対策のために敷くのは避けるようにしましょう。
5-6. 敷布団の洗い方は?
「洗える敷布団」以外は洗えません。
繊維が固まりダマになるため寝心地が一気に低下するからです。そのため、洗えることを重視しているなら、洗えることが明記されている敷布団を選ぶようにしましょう。
とはいえ、洗える敷布団はクッション性が低いものが多いため、寝心地の観点からはあまりおすすめできません。寝心地が良い敷布団を洗う必要がないよう保護して使うことをおすすめします。
5-7. クリーニングに出すのは可能?
家で洗うことができない敷布団は、クリーニングに出してキレイにしましょう。
基本的にクリーニング可能ですが、ダメなものやドライクリーニングのみのものがあります。
- 固わた入りは基本不可
- ウレタン入りは基本不可
- 磁石入りは不可
- 羊毛・キャメルはドライクリーニング
こちらページ『敷布団クリーニングの料金、素材別注意点などのまとめ』で料金などをご説明しているので合わせてご参考にしてください。
最後に
あなたが素晴らしい敷き布団を選ぶための一助になっていれば幸いです。
著者紹介

著者情報
加賀 照虎(上級睡眠健康指導士)
上級睡眠健康指導士(第235号)。3,000万PV超の「快眠タイムズ」にて睡眠学に基づいた快眠・寝具情報を発信中。NHK「あさイチ」にてストレートネックを治す方法を紹介。取材依頼はこちらから。
各種SNSで情報発信中。
上級睡眠健康指導士(第235号)。3,000万PV超の「快眠タイムズ」にて睡眠学に基づいた快眠・寝具情報を発信中。NHK「あさイチ」にてストレートネックを治す方法を紹介。取材依頼はこちらから。
各種SNSで情報発信中。







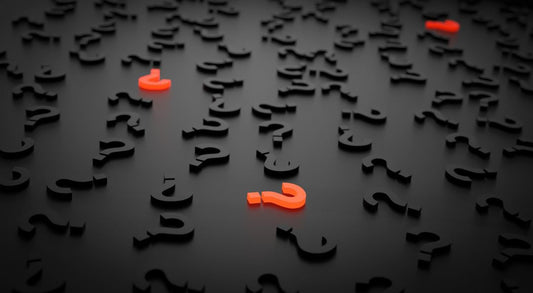


「いくら眠っても眠い」
「寝付きが悪くなった」
など睡眠のお悩みを抱えてはいないでしょうか?
多くの研究データから質の低い睡眠は生活の質を下げることがわかっています。
快眠タイムズでは、皆さんの睡眠の質を向上させ、よりよい生活が送れるように、プロの視点から睡眠/寝具の情報を発信していきます。