布団にカビが生えた時の正しい対処法と予防対策まとめ
更新日:

こんにちは、加賀照虎です。
布団にカビが生えていてお困りではないでしょうか?
カビが生えた布団を使っていると、健康に悪い影響を及ぼす可能性があるので即刻対処が必要です。
そこで本日は、
- 敷布団にカビが生えてしまった場合の対処法
- 二度と同じ被害を繰り返さないための対策
などについて分かりやすく解説していきます。
1. カビが生える原因は?身体に悪いの?
それでは先ず、カビが生える原因と健康への悪影響をご説明します。
1-1. カビが生える原因は?
カビは菌です。生き物です。
空気中に浮遊し広がり、1㎥当りに少なくとも数個、多いと数千個は存在しています。
そして、あらゆるところに付着し、好ましい環境で一気に繁殖します。
カビが好む環境は、以下のようなところです。
- 高湿度(80%以上)
- 暖かい温度(20 ~ 30℃)
- 豊富な栄養源
そして、残念なことに、ヒトの寝床はこの条件を全てクリアしています。
- 高湿度:寝汗や気化熱(蒸気としての汗)、梅雨
- 暖かい温度:ヒトの体温
- 栄養源:剥がれ落ちた皮膚、皮脂、フケ、アカ、ホコリ
そのため、布団の手入れを怠ると、いつカビが発生しても不思議ではない状態なのです。
また、布団が敷きっぱなしの万年床になっていたり、窓や床に結露が発生するような環境だと湿気が布団にたまる一方なので、さらにカビ発生のリスクを高めます。
1-2. 身体への悪影響は?
カビは以下のような悪影響を健康に及ぼす可能性があります。
アレルギーをお持ちの人、身体が敏感な人、免疫力の少ない子供、体力に衰えを感じている人、免疫力の少ない子供は特に注意が必要です。
-
アレルギー疾患
空気中のカビの胞子を吸い込むことで、気管支ぜんそく、鼻炎、結膜炎などを引き起こすことがあります。「寝室へ行くと喉・鼻の調子が悪くなる」という人は、症状が出ているのかもしれません。 -
感染症
カビが身体に取り付くことにより感染症にもなります。最も多いのが「足白癬」で足が白くカサカサになるタイプの水虫です。体内まで侵されると「カンジタ症」などを引き起こします。
そのため、カビを発見したら早めに除去・クリーニングをしましょう。
2. 布団や敷布団にカビが生えたとき捨てるべき?それとも使える?
布団にカビが生えたときは「軽度なら使える、重度なら買い替え」が基本です。うっすら白カビ程度なら漂白や除菌、除湿機や天日干しで対応できますが、黒カビが広範囲に出たりカビ臭が強い場合は処分を検討すべきです。
布団は寝汗や加齢臭を吸収しやすく、一度根を張ったカビはアレルゲンとなり健康被害のリスクもあります。敷きっぱなしを避け、通気性を確保しつつ、シリカゲルや防カビ加工・抗菌寝具を活用すれば予防可能です。
迷ったら無理に使い続けず、新しい布団に替えるのも賢い選択です。
3. 布団や敷布団のカビを落とす方法
それでは次に、敷布団にカビが生えた場合の対策をご紹介します。
(※ウレタンマットレスは対象外です。)
3-1. 自分でカビを除去する4つのステップ
カビの被害がひどくなければ(カビの広がりが一部で、発見が早い場合)、あなた自身でも除去することができます。
以下のものを用意します。
|
そして、以下の4つのステップで除去していきます。
20分もあれば完了します。(※部屋の換気を良くして行いましょう。)
- まずは水で湿らしたティッシュで布団表面のカビ菌を取りましょう。カビ菌が飛散しないよう、ティッシュはすぐさまゴミ袋へ。
- 次に、漂白剤代わりに重曹水でカビのある箇所を湿らします。2~3分時間をおいてから、たたく様に拭き取ります。
- そして次に、カビのある箇所をエタノールで滅菌します。2~3分時間をおいてから、たたく様に拭き取ります。
- 干して乾燥させます。生乾きだと、またカビが発生する原因になります。お気をつけください。
カビ取り用洗剤などの方がカビ取り効果は強いと思いますが、素肌に触れる寝具のクリーニングなので、低刺激でより安全性の高い重曹(pH8強)を使用する方法をご紹介しました。

もしカビの状態がひどい場合、ご自身でカビ取りを行うよりもクリーニング店にお願いする方が良いでしょう。
3-2. 自分でできそうにないならクリーニングに出す
カビが思ったより深刻だったり自分でカビ除去をする時間がない人は、クリーニングに出すことをおすすめします。
例えば、こちらのアイクリーンサービスでは、敷布団は1枚5,600円でクリーニングをしてくれ、1,000円追加でカビ取りサービスをしてくれます。
また、クリーニング中の敷布団レンタルサービスもあります。自分でカビ取りをするよりは費用がかかりますが、敷布団が完全にキレイになることを考えるとアリだと思います。
3-3. 敷布団を買い換える
あまりにもカビがひどくクリーニングを受け付けてもらえなかったり、そもそも使用期間が長く寝心地が悪くなっているのであれば、買い換えるタイミングと発想を転換しても良いかもしれません。
以下のページで敷布団の選び方(腰・背中をリラックスさせて眠るためのサポート性、キレイに維持するための衛生性、日常生活を楽にするための取扱性)をご紹介しています。是非あわせてご参考にしてみてください。
関連記事:【熟睡敷布団のおすすめ9選】正しい選び方3つのコツ
ただ、敷布団を新しくするとはいえ、新しい敷布団でも今までと同じような使い方をしていると、またカビを生やしてしまう可能性があります。そこで3章では、敷布団のカビ予防となる事前対策をご紹介します。新しい敷布団の衛生管理のために確認しておきましょう。
4. 布団や敷布団のカビの予防対策

事故や病気は事前に防ぐことが大切です。
こちらでご紹介するカビの予防対策を行っていただければ、寝具のカビとは疎遠になることができます。
4-1. カビ予防対策リスト
先にも言いましたが、カビの原因は「高湿度・暖かい温度・栄養源」です。
これらの要素を少なくするために、以下のリストの対策を行いましょう。
- 敷布団は定期的に天日干しをする。乾燥させることでカビの繁殖を防ぎます。汗や汚れも軽減することができます。
- 朝起きたら敷布団を押入れにしまう。敷きっぱなしは湿度が敷布団と床の間に熱と湿気が溜まりっぱなしになるので厳禁です。
-
しまう場所がない場合、少なくとも敷布団をめくっておく。敷布団をめくっておくことで、熱と湿気が溜まりっぱなしになることを防ぎます。

布団をめくって乾かす - 寝室の換気を頻繁にする。部屋の湿度が高くなる場合は、換気をして湿度を下げましょう。
- 敷寝具(ベッド)を壁にくっつけて使わない。壁と接している場合、空気の流通が悪くなりがちです。10cmで良いので隙間をつくりましょう。
- たまに敷寝具をひっくり返して使う。同じ面ばかりが寝汗で湿気ることを防ぐために、定期的にひっくり返しましょう。
- シーツを頻繁に取り替える。シーツにはカビの栄養源(剥がれ落ちた皮膚、皮脂、フケ、アカ、ホコリ)がたまるので、カビを育てる原因になります。
- カビ予防になる寝具アイテムを使う。カビが発生する原因の湿気や栄養源を敷布団・マットレスから減らす働きをします。【3−2】にて詳細をご紹介します。
ご家庭の設計・構造により、風通しの良し悪しが異なります。負担にならないことから対策していきましょう。ある程度対策してたのにカビの被害にあった人は、次に紹介するアイテムを使ってみることをオススメします。
4-2. カビ予防に効果のある寝具アイテム
敷布団(ウレタンマットレスも)カビ予防ができるオススメの寝具アイテムが4つあります。
4-2-1. 除湿敷きパッド
敷きパッドは寝汗、皮脂、フケ、アカから敷布団・マットレスを守るため、カビ対策に重要な働きをします。1枚敷いて置くだけで安心です。

- 製品:快眠タイムズ 除湿・消臭敷きパッド
- 価格:5,980円
- 【購入ページはこちら】
自社製品で恐縮ですが、コーミング加工をした高品質な綿100%の敷きパッドです。お菓子の袋の中によく入っている除湿剤のシリカゲルを中材に詰めているため寝汗をとてもよく吸収します。熱帯夜でもカラッと爽やかに眠れます。また、シリカゲルには消臭効果もあるので、汗臭、加齢臭、タバコ臭などもスッキリ除去します。
4-2-2. プロテクター(防水シーツ)
まだあまり知られていない方法ですが、防水のプロテクターを使うのも有効です。

- 製品:プロテクト・ア・ベッド プロテクター
- 価格:5,500円
- 【購入ページはこちら】
敷布団の中に寝汗が入っていかないので、敷布団内の湿度が上がりにくくなります。さらに皮膚、皮脂、フケ、ホコリなどの栄養源も敷布団の内部にたまらないので、カビ発生の予防になります。寝汗をよくかく人、フケが出やすい人にとてもオススメです。自社製品で手前味噌ですが、No.1の防水マットレスプロテクター(防水シーツ)と自負しています。
4-2-3. すのこ(すのこベッド)
すのことは、角材の上に薄い板を取り付けたものです。

- 製品:みやび格子すのこベッド 二つ折りタイプ
- 価格:20,200円(税込)
- 【商品ページはこちら】
今お使いの敷布団をすのこの上に置くことで、敷布団の底に湿気がたまりにくくなり、カビの予防になります。フローリングに敷布団を直置きしている人にオススメです。とはいえ、すのこがあれば他の対策はしなくて良いというわけではありません。
4-2-4. 除湿シート(除湿マット)
除湿シートとは、吸湿性の高い繊維や素材(主にシリカゲル)で作られたシートです。敷布団の下に敷くことで、底にたまりがちな湿気を吸収してくれ、カビの予防になります。

- 製品:洗える除湿シート
- 価格:1,540円
- 【商品ページはこちら】
弊社が開発した除湿シートです。シリカゲル素材を使っているので吸湿だけでなく、汗臭や加齢臭などの消臭効果もあります。2週間に1度は干すようお願いします。除湿シートにも「吸った湿度を吐き出させる」時間が必要なのです。敷布団の下に敷きっぱなしだと、除湿シートにもカビが生えるのでお気をつけください。
5. カビが生えにくい布団の選び方とは?
布団は寝汗や湿気を吸収しやすいため、放っておくとカビが発生しやすい寝具です。そこで大切になるのが、そもそも「カビが生えにくい布団」を選ぶことでしょう。ここでは、布カビが生えにくい布団の選び方について解説していきます。
5-1. 吸放湿性に優れた天然素材を選ぶ
放湿性が高く湿気がこもりにくい素材としては、羊毛が特におすすめです。「綿は吸湿性は高いものの、放湿性はやや劣る。対して羊毛は湿気を吸って放出する能力が2倍ほど高く、結果としてカビが生えにくい」との声があります。
5-2. 通気性・速乾性を確保できる構造
通気性の悪い敷きっぱなしでは、カビのリスクが高まります。湿気を逃がしやすい構造や素材、そして「すのこ」+布団の併用で通気性を大幅に改善するのが効果的です。
5-3. 吸湿・速乾・防カビ加工の寝具を活用
通気性に加えて、防カビ・抗菌加工やシリカゲルなど湿気取り素材が使われた寝具もおすすめです。これによりカビの発生をさらに防げます。
6. 布団のカビを防ぐ部屋の環境作りのコツ
布団のカビ対策は寝具そのものだけでなく、部屋の環境作りも大切です。カビは「湿度・温度・栄養源(皮脂やホコリ)」が揃うと一気に繁殖します。
そのため、部屋の空気環境を整えることで、布団のカビリスクを大幅に下げられます。
6-1. 室内の湿度管理
カビが発生しやすい湿度は60%以上なのです。布団のカビを防ぐためには、室内の湿度を40〜60%に保つことが理想的です。
梅雨や夏場は湿度が上がりやすいため、除湿機やエアコンの除湿運転を活用しましょう。冬場は加湿器を使う場合でも、過剰加湿による結露に注意が必要です。
6-2. 室温と換気
カビは20〜30℃で活発に繁殖します。エアコンの冷房・暖房を上手に使い、急激な温度差を避けながら安定した室温を維持しましょう。また、窓を開けての換気やサーキュレーターを使った空気循環も有効です。
6-3. 家具や寝具の配置
布団を敷く場所に空気の通り道を作ることもポイントです。
壁や家具にぴったり付けて布団を敷くと湿気がこもりやすくなるため、少し隙間を空けましょう。収納時も押入れに詰め込みすぎず、除湿剤やシリカゲルを併用すると効果的です。
6-4. 生活習慣の工夫
寝汗や加齢臭による皮脂汚れもカビの栄養源になります。寝具の洗濯や天日干しをこまめに行い、部屋の掃除でホコリやダニの温床を作らないよう心がけましょう。
最後に
自分でクリーニング、クリーニング店に出す、新しく買い替える、あなたの敷布団の状況に合わせて対策を行いましょう。
もし、新しく敷布団を買い直す場合は、予防対策をしっかり行いましょう。
二度とカビ被害に合わなければ幸いです。
よくある質問
Q1. 布団のカビはどれくらいで健康被害が出るの?
A.布団にカビが発生してもすぐに症状が出るわけではありませんが、カビの胞子を吸い込み続けることで、数日〜数週間のうちに健康被害が現れる可能性があります。
- 主な症状は以下の通りです。
- アレルギー性鼻炎・咳・くしゃみ
- 気管支喘息の悪化
- 皮膚のかゆみ・湿疹
- 免疫力の低下による体調不良
特に小さなお子さまや高齢者、アレルギー体質の方は影響を受けやすいため注意が必要です。見た目に異常がなくても、湿気がこもったままの布団にはカビが発生していることもあるため、定期的な確認とケアが重要です。
Q2. 防ダニ布団や防菌仕様でもカビは生える?
A.はい、防ダニ布団や抗菌・防臭加工が施された布団であっても、湿気がこもればカビが発生する可能性は十分にあります。
防ダニや防菌仕様は以下を対象にしています。
- 防ダニ:ダニの侵入・繁殖を防ぐ
- 抗菌:菌の増殖を抑える(※カビ菌も含むが、効果は限定的)
しかし、カビの原因は湿気や寝汗による水分の蓄積であるため、通気性の確保や定期的な乾燥が不可欠です。「防カビ効果があるから安心」と油断せず、日常の布団ケアを並行して行いましょう。
Q3. 黒い点のようなカビは放っておくとどうなる?
A.黒い点のようなカビは、黒カビ(クラドスポリウム属)などの真菌の一種で、放置すると急速に広がる危険性があります。
放置することで起きるリスクは下記になります。
- 布団の内部までカビが浸透し、丸洗いでも除去できなくなる
- アレルギー症状やカビ臭の悪化
- 布団素材そのものが劣化・変色する
また、黒カビは空気中に胞子を放出するため、他の寝具や部屋の壁紙にも被害が広がることがあります。早めの除去と、必要であれば買い替えを検討するのが安全です。
Q4. 布団がカビ臭いけど見た目はきれいな場合は?
A.カビ臭がするのに見た目がきれいな場合、布団の内部に目に見えないカビが繁殖している可能性が高いです。特に、湿気がこもりやすい綿やウレタン素材の敷布団では、外からは分からなくても内部でカビが進行していることがあります。
対策としては、
- 布団乾燥機(高温モード)で内部の湿気を取り除く
- 重曹やクエン酸を使った消臭・除菌スプレーでケアする
- 臭いが取れない場合や使用中に咳・かゆみが出るなら、買い替えも検討
見た目だけで判断せず、においや肌トラブルなど体の反応も目安にしてケアを行いましょう。
Q5. 布団に生えたカビを掃除機で吸っても大丈夫?
A.カビを掃除機で吸い取るのは、一時的な表面の胞子除去には効果的ですが、根本的な除去には不十分です。
注意点としては、
- 掃除機の排気によってカビ胞子が部屋中に拡散してしまうリスクがある
- HEPAフィルター付きの掃除機を使用するのが理想
- カビの根が内部にまで入り込んでいる場合は、掃除機だけでは完全に除去できない
掃除機を使った後は、アルコールスプレーや除菌剤を併用し、しっかり乾燥させることが大切です。広範囲にカビが生えている場合は、専門業者への依頼か買い替えが無難です。
著者紹介

著者情報
加賀 照虎(上級睡眠健康指導士)
上級睡眠健康指導士(第235号)。3,000万PV超の「快眠タイムズ」にて睡眠学に基づいた快眠・寝具情報を発信中。NHK「あさイチ」にてストレートネックを治す方法を紹介。取材依頼はこちらから。
各種SNSで情報発信中。
上級睡眠健康指導士(第235号)。3,000万PV超の「快眠タイムズ」にて睡眠学に基づいた快眠・寝具情報を発信中。NHK「あさイチ」にてストレートネックを治す方法を紹介。取材依頼はこちらから。
各種SNSで情報発信中。







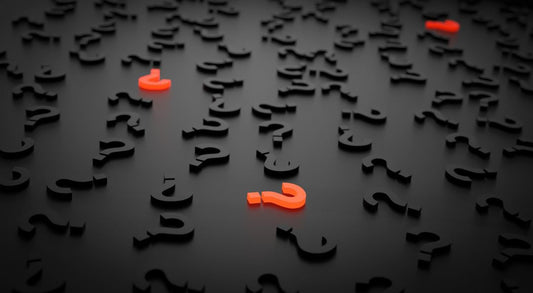


「いくら眠っても眠い」
「寝付きが悪くなった」
など睡眠のお悩みを抱えてはいないでしょうか?
多くの研究データから質の低い睡眠は生活の質を下げることがわかっています。
快眠タイムズでは、皆さんの睡眠の質を向上させ、よりよい生活が送れるように、プロの視点から睡眠/寝具の情報を発信していきます。