敷布団は洗える?自宅・コインランドリーでの洗濯方法と注意点
更新日:

敷布団をシーツで汚れから守っていたはずが、よくよく気づくとかなりのシミや汚れで当惑してはいないでしょうか?
しかし、「今すぐ敷布団を洗濯して汚れを落としたい」と思っても、適切な洗濯方法が分からずお困りかと思います。
そこで本日は「敷布団の洗濯方法とそのリスク」についてご紹介します。
| ※敷布団の素材別の特徴、機能性を比較した選び方についてこちらのページ「【熟睡敷布団のおすすめ9選】正しい選び方3つのコツ」で徹底解説しています。汚れが落ちそうにないから買い替えようかなとお考えでしたらぜひ参考にどうぞ。 |
1. 敷布団の洗濯に伴う寝心地悪化のリスク
あなたがご自身で敷布団を洗濯や脱水をすると、寝心地を悪化させるリスクがあることはご了承ください。
例えば、敷布団の中材(ポリエステル、木綿、ウールなどのわた)が偏ったり、ダマになったり、ヘタったりすることで、寝心地が硬めになってしまったり、凸凹してしまう可能性があります。
また、芯材(固綿やウレタンフォーム)のある敷布団だと、さらに劣化が激しいです。特にウレタンフォームは水に弱いので、破損の可能性も覚悟しておきましょう。
2. 敷布団は洗濯できない素材もある?確認方法と見分け方
敷布団はすべてが丸洗いOKというわけではなく、素材や加工によっては自宅での洗濯が向かないものもあります。間違った洗い方をすると中綿が偏ったり、乾きにくくカビや臭いの原因になることも。
ここでは、洗濯可能かどうかを見極めるための 洗濯表示タグ・中材・見た目のポイント を整理します。
2-1. 洗濯表示タグを確認する
まずは布団に縫い付けられている洗濯表示タグを確認しましょう。
| 表示マーク | 洗濯可否 | ポイント |
|---|---|---|
| 洗濯機マーク | ◎ 洗濯機で丸洗いOK | 脱水や乾燥機対応なら天日干しとの併用で衛生管理しやすい |
| 手洗いマーク | ○ 手洗い可能 | 型崩れを防ぐため押し洗い。洗濯頻度は控えめに |
| 水洗い不可 | × 自宅洗濯NG | 無理に洗うと中綿が偏るため要注意 |
| ドライマーク | × 水洗い不可 | 専門の布団クリーニング店へ依頼が安心 |
タグは最も確実な判断基準です。「水洗い不可」や「ドライ」と表示されている布団は自宅での丸洗いを避け、乾燥機や布団乾燥機、天日干しなどで日常の衛生管理を行うのがおすすめです。
2-2. 中材で判断する
中材(中綿の種類)によっても洗濯可否は変わります。
| 中材 | 洗濯可否 | 特徴・注意点 |
|---|---|---|
| ポリエステル・アクリルなど化繊 | ◎ 洗濯しやすい | 丸洗いOK。速乾性が高く衛生管理が簡単。洗うとダマになることも |
| 固綿入り布団 | △ 素材次第 | 洗える場合もあるが、厚みがあると乾きにくい |
| ウレタン | × 洗濯不可 | 水を吸うと乾きにくく、カビや臭いの原因に |
| ファイバー | ◎ 手洗い可 | シャワーで水洗いができる |
| 羊毛100% | × 洗濯不可 | 水に濡れると縮みやすくクリーニング推奨 |
| シルクなど高級素材 | × 自宅洗濯NG | 繊細で漂白剤不可。専門店に相談が安全 |
洗える布団を探すなら、ポリエステルなど化繊素材が安心です。逆に、ウレタンや羊毛は水に弱く、自宅洗濯には不向き。中材をチェックしてから洗濯の可否を判断することで、布団の寿命を守れます。
2-3. 見た目や加工での簡易判断
中材やタグだけでなく、布団の見た目や縫製加工からもヒントを得られます。たとえば キルティング加工(中綿を縫い留める縫製) がある布団は洗濯しても中綿が偏りにくいため比較的扱いやすいです。
一方、加工がされていない布団は洗濯時に中綿が寄りやすく、部分的に厚みが変わってしまうことがあります。
3. 敷布団の洗濯方法
それでは次に、敷布団の洗濯方法を自宅でのやり方と、コインランドリーでのやり方に分けてご紹介します。
3-1. 自宅で洗濯するならお湯で押し洗い
敷布団を自宅で洗濯するなら、中材のわたを劣化させないように優しく押し洗いをするようにしましょう(ウレタンが水に弱いものだとひどく劣化する可能性あり)。
以下の手順で洗濯します。
- 浴槽にお湯を貯める
- 三つ折りにした敷布団を浴槽に沈める
- 押し洗いをする(足で踏むと楽)
- 汚れやシミが目立つなら洗剤を使う
- 押して水気を切る
- 乾燥させる
洗剤は天然素材に優しい中性洗剤を推奨します。
しかしもし、おねしょ汚れで敷布団にニオイが残っているのなら、クエン酸やレモン汁のような酸性の力でニオイを中和させましょう。

また、敷布団を乾かす時、直射日光に当て過ぎないように気をつけましょう。
側生地が日焼けをして傷んでしまう恐れがあります。予め時間に余裕を持たせて、日陰干しメインでゆっくり乾かしましょう。
3-2. コインランドリーで洗濯するなら敷布団を紐で縛る
コインランドリーでの洗濯は敷布団にとって過酷なため、使用感の悪化はさらに激しいです。
そのため、あまりおすすめできる方法ではありません。そもそも、コインランドリーの店側が、敷布団の洗濯を受け付けていないこともあります。
しかし、何らかの事情で敷布団を自宅で洗濯できないのなら、以下のように敷布団を紐で縛ってから洗うことで劣化を抑えられます(洗浄力も若干落ちますが)。

紐は天然繊維のものをおすすめします。ビニール紐だと洗濯中にツルッと取れてしまいやすいです。
また、洗濯時間と乾燥時間は、機械ごとに変わりますので店側と相談して決めることをおすすめします。
4. おねしょ・嘔吐・カビが発生した場合の対処法
おねしょで布団が濡れてしまった場合は、できるだけ早く対処することがカビや臭い防止のポイントです。布団の状態や汚れの範囲に応じて、部分洗いと丸洗いを使い分けましょう。
4-1. 敷布団がおねしょで汚れた際の対処・洗濯方法
汚れた範囲が狭い場合は、以下の手順で部分洗いしてください。
- 洗濯表示を確認し「手洗い可」であることを確認する
- 濡れた部分にタオルやペットシートを押し当てて水分を吸い取る
- 40℃以下のぬるま湯で汚れを流す
- 乾いたタオルで水分を拭き取る
- 天日干しでしっかり乾かす
汚れた範囲が広いときは、以下の手順で自宅で丸洗いしましょう。
- 晴れの日を選び、しっかり乾かせるタイミングで行う
- 浴槽に40℃以下のぬるま湯をため、中性洗剤を溶かす
- 布団を入れて足踏みして洗う
- シャワーですすぎ、浴槽のふちにかけて水を切る
- 物干し竿を2本使って「M字干し」にして天日干しする
部分洗いであれば手間を抑えて対応できますが、範囲が広い・繰り返し汚れて黄ばみが目立つ場合は丸洗いが効果的です。いずれの場合も、中までしっかり乾燥させることが大切です。
4-2. 布団に嘔吐した時の洗い方
子どもが感染性胃腸炎などで突然嘔吐してしまうと、夜中であっても布団や毛布が汚れてしまうことがあります。慌てて処理をするとウイルスを吸い込んで二次感染のリスクが高まるため、落ち着いて正しい手順で対応することが大切です。
嘔吐直後、すぐに布団が洗えない場合は、以下の手順で応急処置を施しましょう。
- ウイルスが体内に入らないように、使い捨て手袋とマスクを必ず装着する
- 汚れを外側から内側へ向けて嘔吐物を静かに拭き取り、使った布は消毒液に浸けて廃棄する
- スチームアイロン・熱湯・布団乾燥機などに熱でウイルスを不活化する
汚れを外側から内側へ向けて嘔吐物を静かに拭き取り、使った布は消毒液に浸けて廃棄する
スチームアイロン・熱湯・布団乾燥機などに熱でウイルスを不活化する
自宅で洗う場合は、嘔吐物を処理したあとに布団や毛布を100倍に薄めた塩素系消毒液に10分ほど浸してから洗濯を行います。色柄物の布団で塩素系消毒液が使えない場合は、洗剤を溶かした水でもみ洗いをし、しっかりとすすいだあとに85℃以上の熱湯で1分以上浸すと安心です。
一方でクリーニングに出す場合、通常の店では断られることが多いため、消毒処理が可能な「指定洗濯物取扱施設」に依頼しましょう。施設の場所は保健所やWebで確認できます。
4-3. 布団のカビ取り方法
敷布団やカバーにカビが発生すると見た目だけでなく衛生面でも心配です。放置するとアレルギーや臭いの原因にもなるため、早めに対処しましょう。ここでは、自宅でできる代表的な方法を紹介します。
4-3-1. 敷布団は重曹で拭き取る
まずは家庭で取り組みやすい、重曹を使った拭き取り方法です。重曹は安全性が高く、軽いカビであれば十分に効果を発揮します。
- 水またはぬるま湯300mlに重曹大さじ2を混ぜ、スプレーボトルで重曹スプレーを作る
- カビ部分に吹きかけて3分置く
- 浮き上がったカビをつまむように拭き取り、エタノールを全体にスプレーして5分置く
- 清潔な布で叩くように拭き、水拭き後によく乾かす
この方法は軽度のカビに有効ですが、完全に落とすには複数回繰り返す必要がある場合もあります。
4-3-2. 重曹で落とせない場合はカビ除去スプレーを使用
重曹で落としきれない頑固なカビには、市販のカビ除去スプレーが役立ちます。ただし、漂白作用が強いため必ず色落ちの確認をしてから使用しましょう。
- まずは目立たない部分で色落ち確認
- 問題なければカビ部分に直接スプレーし30分置く
- 落ちない場合は繰り返し、落ちたらそのまま乾かす(※水拭き不要)
この方法は強力ですが、布団生地を傷める可能性もあるため、あくまで最終手段として考えると安心です。
4-3-3. シーツや布団カバーのカビ取り
布団本体に比べてシーツやカバーは洗濯機で手軽に丸洗いできます。漂白剤をうまく使い分けることで、見た目も衛生面もすっきりさせられます。
漂白剤には「酸素系漂白剤」と「衣料用塩素系漂白剤」があります。色柄物は酸素系漂白剤を使いましょう。洗濯機に規定量の漂白剤を溶かし、1時間浸け置きしてから通常洗濯します。
真っ白な生地の場合は衣料用塩素系漂白剤を使います。強力なためマスク・手袋着用、換気を徹底して使用してください。カバー類は布団本体よりも手入れしやすいため、定期的に洗濯して清潔に保つのがおすすめです。
5. 洗濯できない場合の代替案:クリーニング or 買い替え?
敷布団を家庭で丸洗いするのが難しい場合、「クリーニングに出す」か「新品に買い替える」かで迷う方も多いと思います。どちらにもメリット・デメリットがあるので、下の表を参考に自分に合った選択肢を検討しましょう。
| 項目 | クリーニング | 新品購入 |
|---|---|---|
| 清潔さ | 専門洗浄で汚れやダニを除去。ただし完全に新品同様にはならない | ダニ・汚れゼロ。衛生面で最も安心 |
| コスト | 平均1,700〜9,500円程度(方法により幅あり) | 数千円〜数万円。やや高め |
| 利便性 | 短期間で再利用可能。宅配なら自宅から出せる | 選定・購入の手間があるが、届けばすぐ使える |
| 布団の寿命 | 洗浄により延命できるが、劣化は避けられない | 新品なので長く使える |
| 向いているケース | 今ある布団を活かしたい/費用を抑えたい場合 | 徹底的な衛生対策をしたい/長期使用を考えている場合 |
クリーニングはコストを抑えつつ再利用できる点が魅力ですが、布団の状態によっては効果が限定的なこともあります。一方、新品購入は初期費用がかかるものの、清潔さと長期使用の安心感があります。
「今ある布団をまだ活かしたいか」それとも「思い切って清潔さを優先したいか」で判断するとよいでしょう。
最後に
ご紹介の方法で敷布団を極力痛めることなく、キレイに洗えていれば幸いです。
また、もしあなたが「リスクをとってまで敷布団を洗濯するのはちょっとな、、、」とおかんがであれば、以下のページで綿、羊毛、ポリエステルなどの素材別に、腰・背中をリラックスさせて眠るためのサポート性、キレイに維持するための衛生性、日常生活を楽にするための取扱性、の3つの点から敷布団の選び方をご紹介しています。あわせてご参考にしてみてください。
関連記事:【熟睡敷布団のおすすめ9選】正しい選び方3つのコツよくある質問
Q1. 敷布団は何回くらい洗える?寿命に影響する?
A.敷布団は素材によりますが、3〜5回程度の洗濯でへたりや中綿の偏りが起きやすくなるため、洗いすぎは寿命を縮める原因になります。特にポリエステルや綿わたの敷布団は、水分を吸うと重くなり、脱水時にダメージを受けやすいです。
- 長持ちさせるには以下のポイントが重要です。
- 洗濯頻度は年1〜2回程度が目安(汚れた場合は都度)
- 洗濯後はしっかり乾燥させてカビ・ダニの繁殖を防ぐ
- 汚れを防ぐために敷布団カバーやパッドを併用する
洗えるタイプであっても、洗濯回数には限度があり、定期的な買い替えやクリーニングの活用も検討しましょう。
Q2. 防水カバーを使えば洗わなくても大丈夫?
A.防水カバーは、汗・おねしょ・汚れの浸透を防ぐ点では非常に有効ですが、敷布団自体の洗濯が一切不要になるわけではありません。
- 防水カバーの役割は下記になります。
- 汗や皮脂の吸着をブロックして中綿の劣化やカビの予防に効果的
- アレルゲンやダニの侵入を防ぐ衛生的な寝具環境をキープ
ただし、敷布団内部の湿気はこもりやすいため、定期的な陰干しや布団乾燥機の併用が必要です。また、防水カバー自体も定期的な洗濯が必要なので、完全な“ノーメンテナンス”にはなりません。
Q3. 洗えない素材はどうすれば清潔を保てる?
A.洗えない素材の敷布団(ウレタンフォームやラテックスなど)は、以下の方法で衛生状態を保つことができます。
- 毎週〜月1で陰干し・風通しの良い場所で立てかけ乾燥
- 布団乾燥機でダニ・湿気対策(50℃以上の温風で10分以上)
- 敷布団カバーや除湿シートを併用して汗や皮脂の浸透を予防
- 表面のほこり・ダニ対策に掃除機をかける(低吸引)
また、布団のニオイが気になる場合は消臭スプレー(アルコール不使用)や重曹を使ったケアも有効です。洗えなくても、定期的な通気・防菌ケアで清潔を保てます。
Q4. 晴れた日でも敷布団は部屋干しでも乾く?
A.晴れた日であっても、敷布団を部屋干しする場合は通気性と日照条件により乾きづらいことがあります。特に厚手の敷布団や湿度の高い日には、内部の水分が残ってしまうリスクがあるため注意が必要です。
- 部屋干しで乾かすコツは下記になります。
- 風通しの良い場所に立てかける(片面ずつではなく全面に風が通るように)
- 扇風機や除湿器を併用することで乾燥スピードをアップ
- 朝から夕方まで長時間干す(できれば6時間以上)
部屋干しが難しい場合は、布団乾燥機の活用や、浴室乾燥機との併用もおすすめです。
著者紹介

著者情報
加賀 照虎(上級睡眠健康指導士)
上級睡眠健康指導士(第235号)。3,000万PV超の「快眠タイムズ」にて睡眠学に基づいた快眠・寝具情報を発信中。NHK「あさイチ」にてストレートネックを治す方法を紹介。取材依頼はこちらから。
各種SNSで情報発信中。
上級睡眠健康指導士(第235号)。3,000万PV超の「快眠タイムズ」にて睡眠学に基づいた快眠・寝具情報を発信中。NHK「あさイチ」にてストレートネックを治す方法を紹介。取材依頼はこちらから。
各種SNSで情報発信中。







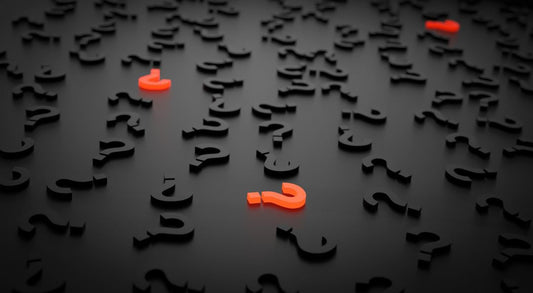


「いくら眠っても眠い」
「寝付きが悪くなった」
など睡眠のお悩みを抱えてはいないでしょうか?
多くの研究データから質の低い睡眠は生活の質を下げることがわかっています。
快眠タイムズでは、皆さんの睡眠の質を向上させ、よりよい生活が送れるように、プロの視点から睡眠/寝具の情報を発信していきます。