子供用布団のおすすめの選び方【サイズと素材を吟味】
更新日:

- 年齢別に適切なサイズ
- 素材の良し悪し
- 適切な硬さ・厚み
などなど、子供用の布団を購入する際に気にならないでしょうか?
また、「価格が高ければ本当に高品質なの?」などとも疑問に感じられるかと思います。
そこで本日は、「子供用布団のおすすめの選び方」についてご紹介します。
1. 子供用布団のおすすめの選び方
子供用布団の「サイズ」「素材」「厚み」「硬さ」の順番におすすめの選び方を説明して行きます。
1-1. 年齢別|子供用布団に適切なサイズ
子供用布団は4サイズあります。
大人用布団(シングル)と比較すると、以下のようになっています(メーカーにより多少の誤差があります)。
| 年齢目安 | 敷布団サイズ | 掛布団サイズ | |
| 新生児布団 | 3ヶ月まで | 60×90cm | 80×100cm |
| ベビー布団 | 3歳まで | 70×120cm | 95×120cm |
| キッズ布団 | 6歳まで | 90×140cm | 120×140cm |
| ジュニア布団 | 15歳まで | 90×180cm | 130×180cm |
| 大人用布団 | なし | 100×200cm | 150×210cm |
「子供の成長に合わせて各サイズの布団を買おうかな」
勿体ないです。
私のおすすめは、新生児のうちからベビー布団で寝かせ、3~4歳になったらもう大人用布団で寝かせてあげる、というものです。もしくは、ずっと大人用布団でも結構です。
というのも、以下の子供の身長の伸び具合のデータをご覧ください(男児のデータですが、女児もほぼ同様の数値になります)。

ご覧の通り、赤ちゃんはすぐに大きくなります(男女ほぼ一緒です)。
新生児用の布団は一年もしないうちに狭苦しく感じられるようになります。ベビー用布団であれば少なくとも3~4歳までは十分に使い倒せます。
同じ理由から、キッズ用とジュニア用もあまりおすすめできないです。1年もしないうちにサイズが足りなくなって押入れで眠らせるハメになった、という話もあります。また、シーツやカバーなどをおしゃれなものにしようとしても、これらのサイズで作られた商品が少ないので非常に選択肢が限られるのもおすすめできない理由です。
1-2. 子供用敷布団に適切な素材
子供用敷布団の素材は以下の4つがメインです。
- 木綿(コットン)
- 羊毛(ウール)
- ポリエステル
- ウレタンフォーム
それぞれ以下のような特徴です。
| イメージ | 反発力 | 吸湿性 | 放湿性 | 洗濯耐性 | 重量目安 | |
| 木綿 (綿/コットン) |
 |
◯ | ◎ | △ | △ | 6kg |
| ポリ エステル |
 |
◯ | △ | - | ◯ | 3.5kg |
| 羊毛 (ウール) |
 |
◎ | ◎ | ◎ | △ | 3.5kg |
| キャメル (らくだ) |
 |
◯ | ◎ | ◎ | △ | 3kg |
| 真綿 (絹/シルク) |
 |
◯ | ◎ | ◯ | △ | 3kg |
| ウレタン フォーム |
 |
◎ | △ | - | △ | 6kg |
「子供は汗っかきだから吸水性にすぐれた木綿がいい」
このような話を聞くことがあると思います。
が、私はとしては洗えるポリエステルやウレタンフォームの敷布団がおすすめです。
理由は以下の2つです。
- 敷布団の上に防水シーツとパッドを敷くため
- もしもの時の掃除が楽なため
敷布団の上に直接子供を寝かせることはありません。
敷布団に防水シーツと敷パッドを敷き、その上に、子供を寝かせます。もしくは、敷布団の上に防水敷パッドを敷きます。

吐き戻しやおねしょなどで、子供はすぐに敷布団を汚します。
その都度、布団を洗うなんて非常に面倒です。しかし、敷パッドだけの洗濯なら楽です。大事故だとしても防水シーツがあればまず敷布団が汚れることはありません。
ただ、万が一、敷布団が汚れてもポリエステル素材の敷布団なら家庭用洗濯機で洗えるものがほとんどですので、何も怖くありません。
また、ポリエステル素材に比べて綿と羊毛は汗の吸い取りにすぐれるためおすすめされますが、防水シーツと敷パッドを敷くとなったら、敷布団の素材の吸水性なんてどれもほとんど一緒になります。それなら、安くて取り扱いが簡単なポリエステルのほうが良いと私は考えます。もちろん、寝心地はこの中では羊毛が一番なので、お財布に余裕があれば、羊毛の敷布団を選ぶのもありです。
1-3. 子供の掛布団の素材は何がいい?
子供用掛布団の素材は以下の3つがメインです。
- 羽毛(ダウン)
- 綿(コットン)
- ポリエステル
それぞれ以下のような特徴です。
| 素材 | 画像 | 保温性 | 吸湿性 | 放湿性 | ドレープ性 | 価格目安 |
| 羽毛 (ダウン) |
 |
◎ | ◎ | ◯ | ◎ | △ |
| 羽根 (フェザー) |
 |
◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ |
| ポリ エステル |
 |
◯ | △ | - | △ | ◎ |
| 木綿 (コットン) |
 |
◯ | ◎ | △ | ◯ | ◯ |
| 真綿 (絹/シルク) |
 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
| 羊毛 (ウール) |
 |
◯ | ◎ | ◎ | ◯ | △ |
子供の寝心地をとるなら羽毛、お手入れの手軽さをとるならポリエステルがおすすめです。
ポリエステルわただとややムレやすいですが、私の経験上、部屋の温度が高かったりしてムレるときは羽毛でもムレます。ただ、掛布団の側生地は(カバーも)絶対に綿のものを選びましょう。
また、子供用の掛布団は軽さが大事だと言われますが、それは新生児や1歳未満の赤ちゃんに対しての話で、布団が重くて苦しかったり、布団内が暑くて辛かったりしても、赤ちゃんが自力で掛布団をどかせないことを懸念してのことです。
私のケースですが、部屋を電気ヒーターで温めて、掛布団ではなくブランケット一枚を掛けて寝かせていました。寝相で布団をはいでしまっても部屋が寒くなければ大丈夫だろう、と考えてのことです。
1-4. 子供用布団に適切な厚み
フローリングや床に布団を直置きして使う予定なら、布団が薄いほうが軽くて押入れからの出し入れなどのお手入れがしやすくいいですよね。
なので、できるだけ薄い敷布団を選ぼうと考えられると思いますが、少なくとも5cmはあるものをお選びください。ポリエステルであろうと木綿であろうと、最低限5cmの厚みはないと寝心地が不安です。
また、もしあなたが敷寝具は布団ではなくウレタンマットレスをお考えでしたら、子供の体重をベースに以下のように厚みをお考えください。(ウレタンは密度30Dを基準にしています。)
- 3cm:1歳(体重10kg)前後
- 4cm:3~4歳前後
- 5cm:7歳(体重30kg)前後
1-5. 子供用布団に適切な硬さ
子供用布団は、中芯に固わたが入っている普通〜硬めのものを選ぶようにしましょう。
柔らかいものはお控えください。
理由は2つあります。
- うつぶせ寝になったとき、鼻や口が布団にうもれてしまって呼吸ができなくなってしまう恐れがあるため。
- 寝姿勢が歪み骨の成長に悪影響を及ぼす恐れがあるため。
低反発ウレタンマットレスの低品質なものにも同じことが言えます。ご留意ください。
1-6. 子供用布団のシーツやパッドの揃え方
「布団セットとか色々あるけど子供のための布団は結局、何を買い揃えればいいの?」
このように疑問を感じると思いますが、これはケース別で異なります。
もしあなたが最低限で済まそうとお考えであれば、【敷布団→防水敷パッド→掛布団(とカバー)】で大丈夫です。もしくは、【敷布団→防水シーツ→敷パッド→掛布団(とカバー)】です。敷パッドの上にシーツを敷いてもいいですが、絶対に敷く必要はありません。

ただ、あなたのご自宅が湿気りやすい、もしくは、あなたが週に1~2度布団を干すことができないのであれば、【除湿シート→敷布団→防水シーツ→敷パッド→掛布団(とカバー)】というふうに、除湿シートを使って布団から湿気を取り除きカビ対策をしましょう。
以下のページで防水シーツを快適に使うための選び方(素材、生地、防水範囲の違いなど)をご紹介しているのであわせてご参考にしてください。
関連記事:目的別に正しく!快適な防水シーツを選ぶ4つの目安とおすすめ最後に
子供用布団を選ぶための参考になっていれば幸いです。
また、もしあなたが「敷寝具は布団じゃなくてマットレスにしようかな」とお考えであれば、こちらのページ『子供用マットレスの選び方5つのポイント』で子供用マットレスの選び方をご紹介しているので、あわせてご参考にしてください。
著者紹介

著者情報
加賀 照虎(上級睡眠健康指導士)
上級睡眠健康指導士(第235号)。3,000万PV超の「快眠タイムズ」にて睡眠学に基づいた快眠・寝具情報を発信中。NHK「あさイチ」にてストレートネックを治す方法を紹介。取材依頼はこちらから。
各種SNSで情報発信中。
上級睡眠健康指導士(第235号)。3,000万PV超の「快眠タイムズ」にて睡眠学に基づいた快眠・寝具情報を発信中。NHK「あさイチ」にてストレートネックを治す方法を紹介。取材依頼はこちらから。
各種SNSで情報発信中。







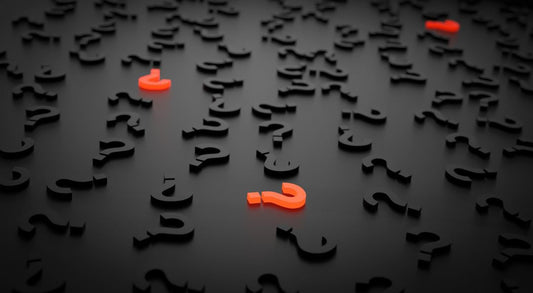


「いくら眠っても眠い」
「寝付きが悪くなった」
など睡眠のお悩みを抱えてはいないでしょうか?
多くの研究データから質の低い睡眠は生活の質を下げることがわかっています。
快眠タイムズでは、皆さんの睡眠の質を向上させ、よりよい生活が送れるように、プロの視点から睡眠/寝具の情報を発信していきます。